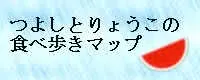本山寺の枕状溶岩の上を歩いて土を見る

前回のアカガシのドングリを探しに本山寺への記事で高槻の本山寺へ行った旨を記載した。
高槻の本山寺といえば、枕状溶岩と出会いに高槻の本山寺へ2の記事で記載したように

大体の箇所が砂岩頁岩互層だけれども、

局所的に海底火山跡があり、粘性の低い枕状溶岩(玄武岩)で構成されている。
この枕状溶岩の露頭が大変興味深くて、

足元には非常に栽培しやすそうに見える黒ボク土のような黒い土が堆積している。
※砂岩頁岩互層の下に堆積している土については枕状溶岩と出会いに高槻の本山寺へ2の記事をご確認ください。
緑泥石から土の形成を考えるの記事で記載した通り、本山寺前で観測できる土は農業従事者にとって知っておくと優位に立てるものだと確信している。
前振りはここまでにしておいて、アカガシのドングリ拾いの際に、本山寺への旧参道?を通ると枕状溶岩の上を歩ける事を知ったので行ってみた。

はじめに砂岩頁岩互層の上を通る。
木の根元辺りで軽く露頭している箇所があるので見てみると、

細かくなった砂岩があった。
記録として木の根元で土化している箇所を見てみると、


色が薄くて目の細かい砂っぽい土であった。
ここから100メートル程歩いたところで、

目的の枕状溶岩の露頭の上にたどり着く。

落ちている石を見ると、緑泥石が風化しかかっていることがわかる。

更に風化している箇所が上の写真の感じ。
気になるのが木の根元の土だろう。

土の色が全然違う。
砂岩の箇所ではどんなに年季の入った木の下を探しても、こんなに黒い土は見当たらなかった。
砂岩と枕状溶岩(玄武岩)という極端に特徴の異なる母岩をこんなに近距離で観測出来るこの場所は貴重だ。
次にこれらの母岩で植生は異なるか?という事が気になるけれども、まだ森林を見る目は持ち合わせていないので、たくさんの場所を歩いて経験を積んだ時、再びここに来よう。
関連記事
アカガシのドングリを探しに本山寺へ
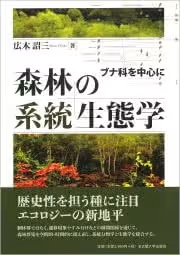
名古屋大学出版会から出版されている広木詔三著 森林の系統生態学 -ブナ科を中心ににアカガシとツクバネガシが標高によって棲み分けをしているという内容が記載されていた。
詳細は標高500m付近で高い方にアカガシ、低い方にツクバネガシが棲み分けているというものだった。
標高を視野に入れて、新たなドングリのなる木を探しに行くことにした。
先日、あくあぴあ芥川にて、標高約520mのところにある高槻の本山寺にスギ林とカシ林があることを知った。
本山寺といえば、枕状溶岩と出会いに高槻の本山寺への記事で山の山頂付近にある海底火山跡を見る為にいったところだ。

山と渓谷社から出版されている林将之著 くらべてわかる木の葉っぱを持って本山寺に向かった。

そろそろ本山寺に到着する辺りから

本に記載されているアカガシの樹皮らしきものを度々見かけるようになった。
この木の根元の落葉をかき分けると、

ドングリが出てきた。

持参した本に記載されている内容によると、アカガシの殻斗は毛がふさふさしているらしく、触ると毛特有の触り心地なので、この木がアカガシである可能性は高そうだ。


この木から展開されている葉には鋸歯がなく、縁が波打っている。
この形態も持参した本に記載されている内容そのものだ。
このドングリを広い、本山寺に向かってみると、境内にある看板にアカガシ林の保護に関する紹介の張り紙があった。
今回のアカガシ探しで興味深かったこととして、アカガシが現れ始める直前の標高に生えていたブナ科の木がアラカシらしき木で、アカガシが現れてからアラカシの木を見なくなった。
本山寺のある山ではアカガシとアラカシが標高によって棲み分けを行っているのだろうか?
また一つ新たな森を見る目が増した。
ハニワ工場公園で出会った新たなドングリの木
コナラのように見えるけれども、このドングリは一体何だ?に引き続き、ドングリを探す。
ドングリは神社仏閣や古墳等の遺跡を探すと良いと何処かで見た。
好都合な事に私が住んでいる大阪府高槻市は今城塚古墳を筆頭に素晴らしい史跡がたくさんあるため、ドングリ探しとしても良質な地域であると言っても過言ではない。
というわけで、

ハニワ工場公園に行ってきた。

ハニワが並んでいる道を通って、公園の奥に向かうと、

足元に見慣れないドングリが落ちていた。

殻斗は二つがくっついた形で落ちていて、

殻斗はうろこ状だ。
このドングリのあった場所の木を見てみると、

肉厚な葉の木があって、

ドングリが付いていた。

念の為に樹皮も記録しておく。

これらの特徴からマテバシイ属か?と頭に浮かんだ。
ただ、マテバシイで新たに得た知見として、


マテバシイ属のドングリは殻斗側が凹んでいるらしく、

今回見たドングリは殻斗側が凹んでいないので、マテバシイ属でない可能性が高い。
帰宅して図鑑を持ち出してみたら、どうやらウバメガシという木らしい。
ウバメガシの説明を読んでみると海岸沿いに多いらしいけれども、街路樹でもよく植えられるという内容も何処かで見かけたので、海から遠い高槻にあっても違和感はない。
実際はどうだかわからないけれども、新たな形のドングリに出会ったのは確か。
高槻の古木、八阪神社のツブラジイ

若山神社のシイ林の記事に引き続き、シイの木探し。
シイの木は神社の御神木として祀られているといった事があるらしいので、大阪の高槻の神社を探してみたところ、

高槻北部の原地区にある八阪神社の境内に


高槻の古木としてツブラジイがあった。
若山神社でみたシイの木と比べると激しく選定されて、枝が短い状態となっていた。

この木は長い間原地区に根付いて、様々な事を経験したのだろうなと、幹を見て感じた。