
前回の生活の身近にいる水草の記事で、イネという抽水植物の水草が水田で生育するために獲得した機能が、ROLバリアで根の先端に酸素を運ぶ形質だということを記載した。
イネの抽水植物以外に水草は他にも3種類あると定義されていて、

植物が完全に水中で生育している沈水植物では、根でROLバリアが発達していようが、そもそも葉が水の外にいるわけではないので意味がない。
沈水植物が水中で生息する上で課題だったことが何であったのか?というと、水中で光合成に必要な光量が届くか?という問題はもちろんのこと、水中で葉が空気を吸収できるか?という問題がある。
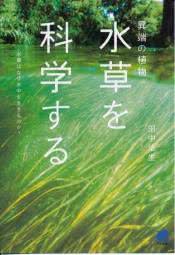
今回も上記の本を参考にして話を進める。
光合成といえば二酸化炭素を吸収して、二酸化炭素と水から有機物を合成しつつ、酸素を排出する行為だ。
植物にとって酸素よりも二酸化炭素の吸収の方が死活問題となり得る。
ここで水中の二酸化炭素の振る舞いについて触れておくと、高アルカリ性の温泉から土を考えるの記事でも触れたが、水中にある二酸化炭素はpHによって形態が異なる。
pHが6よりも低い酸性域では、二酸化炭素(CO2)の形で存在し、pHが6〜10の間では、重炭酸イオン(HCO3-)の形で水に溶けていて、pHが10以上の強アルカリでは、炭酸イオン(CO32-)になるけれども、温泉の時に触れたように強アルカリ環境になるのは難しい。
各水草は遊離二酸化炭素か重炭酸イオンのどちらかの形態で吸収するように進化し、遊離二酸化炭素を吸収するように進化した種では、重炭酸イオンが吸収できないといったように沈水植物の水草は水質(主にpH)の影響を受けやすいと言える。




