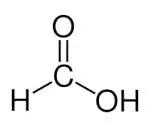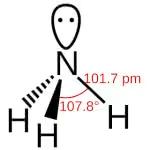/** Geminiが自動生成した概要 **/
近所の道でタンポポを見かけた筆者は、そのがく片が反っていないことに注目。在来タンポポの「カンサイタンポポ」である可能性に喜びを見出します。外来種が多い現代において、がく片が反っていないタンポポを見つけることは、筆者にとって「小さな春を見つけたような、特別な喜び」なのだそう。この記事は、身近な植物の観察から得られるささやかな発見と、その中に宿る大きな喜びを伝えています。あなたも街中でタンポポを見かけたら、ぜひがく片に注目し、在来種か否かを見分けてみてはいかがでしょうか?新しい視点で自然を楽しむきっかけが隠されています。