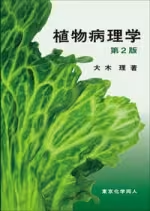/** Geminiが自動生成した概要 **/
養液栽培で肥料不足のため養液交換ができないという相談に対し、根腐れを防ぎながら養液交換回数を減らす方法を検討する。
根腐れの原因は、養液中の溶存酸素低下による糸状菌や細菌の増殖である。
対策としては、紫外線や熱殺菌による殺菌、マイクロバブルによる酸素量増加が考えられる。
さらに、根圏から分泌される成分を制御することで、病原性微生物の増殖を抑えるアプローチも重要となる。
土耕栽培の知見も参考に、根圏環境の改善による根腐れ防止策を探ることが有効である。