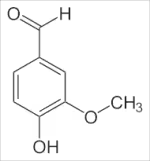/** Geminiが自動生成した概要 **/
湯葉を食した筆者が、「ゆばとは何か?」という疑問から探求を始めた記事。豆腐が豆乳の凝固でできることに触れ、湯葉の製法への関心を示す。Wikipediaで調査した結果、表記はひらがなの「ゆば」が一般的で、「湯葉」「湯波」「油皮」「豆腐皮」といった漢字表記があることを発見。特に地域によって使い分けがあり、京都・大和・身延では「湯葉」、日光では「湯波」と表記されるのが一般的だと判明した。今回は湯葉の名称に関する考察で締め、具体的な湯葉作りについては次回に持ち越すことを予告している。