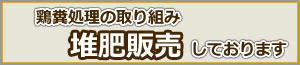少し日が空いたが、家畜排泄物のメタン発酵の際に生成される消化液に土壌改良の効果はあるか?について見ていくことにしよう。
家畜からの排泄物に含まれる有機物の内、真っ先に思い付くのが、植物性の繊維になるだろう。
植物性の繊維を分けると、主に
・不溶性食物繊維(セルロース等)
・水溶性食物繊維(ペクチン等)
あたりになるだろうか。
不溶性食物繊維のセルロースはその名の通り、水に溶けにくいのでメタン発酵を行う場合、大半が固形物の方に蓄積するだろうからここでは触れず、水溶性植物繊維のペクチンについて見ていくことにする。
ペクチンに関しては、

米ぬか嫌気ボカシ肥作りでEFポリマーを加えてみたの記事で触れているので、内容をピックアップしていくと、

ペクチンはガラクツロン酸という糖を主な糖として直鎖状に繋がった多糖類となる。
ペクチンは嫌気性の発酵により下記のように変化する。
ペクチン → ガラクツロン酸 → 酪酸等の短鎖脂肪酸 + 水素(H2) + 二酸化炭素(CO2)
※加水分解菌、酸生成菌
酪酸は嫌気性の発酵により下記のように変化する。
酪酸 → 酢酸 + 水素(H2) + 二酸化炭素(CO2)
※酢酸生成菌
酢酸は嫌気性の発酵により下記のように変化する。
酢酸 → 水素(H2) + メタン(CH4)
※メタン生成古細菌
上記の反応の際、有機酸(短鎖脂肪酸)が生成されるので、ペクチンを溶かした溶液のpHは下がる。
pHが下がれば、排泄物中にある炭酸石灰やリン酸石灰がイオン化して、一部は有機酸との塩が形成されるはず。
水溶性食物繊維はメタン発酵により、大半は有機酸(短鎖脂肪酸) or メタン(CH4) or 水素(H2) or 二酸化炭素(CO2)に変化するということにしておこう。