有機態リン酸の炭化までの記事で、バイオ炭における主要成分の炭化について見てきた。
バイオ炭の農業利用に関しての内容に目を通してみると、低温の炭化と高温の炭化で評価を分けていることがある。
今までの内容だと高温である程、ガスの揮発が多く、純粋な炭素化合物に近づくと予想できるが、他に見るべき内容は何だろう?ということで、
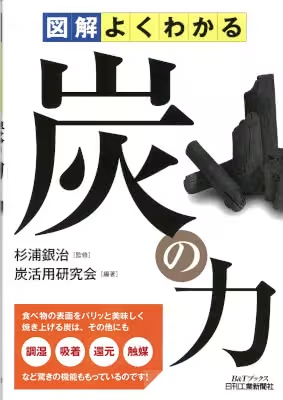
日刊工業新聞社から出版されている図解よくわかる炭の力を読んでみることにした。
どうやら炭作りにおける低温、高温は木の種類によって異なるようで、今回はもみ殻燻炭の温度帯(300℃)を低温として、それよりも高い温度帯を高温とする。
炭の機能の温度帯による明確な差は低温であれば、酸性官能基が多く残り、高温にすると酸性官能基が減り、塩基性官能基が増えるということがある。
これにより、低温ではpHが比較的低くなるが、高温ではpHが高くなる傾向がある。
※炭のpHが高くなる要因は他に炭酸カリの量が増えるということもある。
炭における酸性官能基は主に
・カルボキシ基(-COOH)
・フェノール性水酸基(-OH)
・ラクトン基
カルボキシ基とフェノール性水酸基は栽培で頻繁に話題に挙がる重要な基だ。
一方、炭における塩基性官能基は、
・窒素含有官能基
・酸素含有官能基
・炭素表面のπ電子
であるそうだ。
これらの内容は難しいので詳細は触れないが、炭の塩基性官能基には興味深い特徴があるそうだ。
その特徴というのが、陰イオンの吸着になる。
土壌における陰イオンの吸着といえば、アロフェンのCECとAECの記事で触れたAEC(陰イオン交換容量)だけれども、あまりにも数値が小さいため話題に挙がり難い。
そんなAECだけれども、アロフェンでなくても炭で機能を高められるのは有り難い。



