各ドングリのタンニンの記事に引き続き、ドングリ探しは続く。

陽樹で構成される雑木林のようなところにて、

足元にいが付きのクリを見つける。
クリといえば、ブナ科クリ属の木であるので、クリは広義の意味でドングリと言える。
ちなみにクリの葉がどのような形状であるか?を載せておくと、

こんな感じ。
拾ったクリをハサミやピンセットでこじ開けてみる。

一つのいがから、

大きな球果一つと、

くぼんだ形状のものが二つあった。
クリを調理している方だと、一つのいがから3個の堅果が出てくるのは当たり前かもしれないけれども、

今まで見てきた様々なブナ科の木と比較すると、クリ属が他の属と大きく異なっている事がわかる。
他の属のドングリは一つの殻斗に対して堅果は一つだったけれども、クリは複数個入っている。

これはマテバシイの殻斗にある瘤らしきものは何だ?の記事で見た殻斗の融合によるものであると言えるはず。
実際のところ、ここらへんの定義がどのようになっているか?
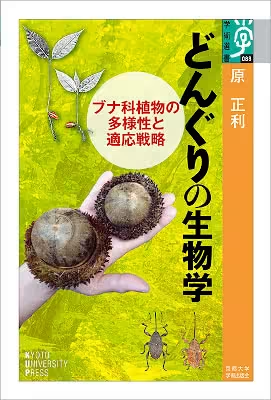
毎度おなじみ、京都大学学術出版会から出版されている原 正利著 どんぐりの生物学 ブナ科植物の多様性と適応戦略を開いてみると、

この本ではクリのように一つの殻斗に複数の堅果があるものを花序殻斗と呼び、

一つの殻斗に一つの堅果を花殻斗と呼ぶことにしている。
※花序殻斗と花殻斗は英語の正式な用語としてはあるが、日本語として正式に決められた用語がない状態
おそらくだけれども、今回のような特徴はブナ科の進化のヒントになるのだろうな。
この特徴を見て、どうしてもこの目で見てみたい木ができた。
その木の元に今年中にたどり着くことが出来るのだろうか?




