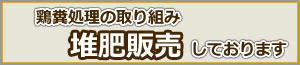牛糞を最初に発酵させる真菌は何だ?の続きまでの記事で、牛糞の発酵処理をステージで分け、ステージ毎にどのような微生物が活性化している可能性があるか?をまとめた。
最初に堆積した糞中に含まれる分解し易い成分である炭水化物やタンパクが利用され、その時に熱を発する。
湯気がでるような高温状態になると、(おそらくであるが)糸状菌(真菌)は活発化できない。
その後、塊が冷めるとセルロース等の繊維やリグニン等の木質の成分が残り、再び糸状菌が活発化する。
この時に活発化する糸状菌はセルロースやリグニンを利用できるものだろう。
ここで真っ先に思い付くのが、白色腐朽菌とトリコデルマだ。
ここで状況を再度整理してみる。
熟成した牛糞を成分分析してみると、硝酸態窒素(無機窒素)とリン酸が多い傾向になる。
上記の傾向を踏まえて頭に浮かぶものとして、白色腐朽菌とトリコデルマの戦いの記事の内容がある。
リグニンとセルロースの分解が得意な白色腐朽菌と、セルロースのみの分解のトリコデルマは競合の関係にあり、培地(今回であれば山積みした牛糞)の無機窒素の量で優劣が決まる。
無機窒素が少なければ白色腐朽菌が優位になり、多ければトリコデルマが優位になる。
であれば、今回の条件ではトリコデルマが優位になり、繊維質の分解のみが積極的に進行する。
ちょっと待てよ。
C/N比や水分量の調整として牛の生糞に藁やオガ屑を混ぜるけれども、これらに含まれるリグニン質の成分は想像するより分解されていない可能性があるのか?
※上記の内容は白色腐朽菌とトリコデルマの競合が発生した場合
これをそのまま土に投入したら、分解前のオガ屑を投入することになり、団粒構造の形成は程遠くなるのではないだろうか?
※分解前のオガ屑は腐植化が進行していない
関連記事
土壌分析でリン酸の数値が高い結果が返ってきたら次作は気を引き締めた方が良い