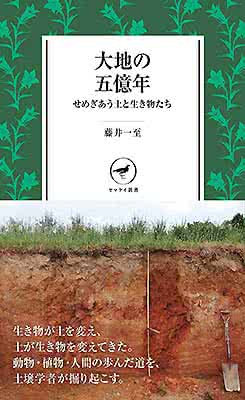
ヤマケイ新書 大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち | 山と溪谷社
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所/大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち
ちょくちょく話題に挙がっている上の本で、森の植林(植樹)についての話題があった。

ハゲ山になったところに対して、いきなり木を植えると定着しにくいけれども、木の周りにシダや低木が充実していると、広葉樹林とかの木が健全に生育しやすいとか。
※文中で記載されている内容は少し異なるけれども、私は上記のように解釈した
以前似たような内容を

光合成速度の高い植物はどこにいる?という記事で記載した。
生態学では当たり前のように草本による腐植の蓄積があってから、その場所に木が根付くという話題があるので、森の植林をする上で広葉樹の苗よりも前に何らかの植物がいることが常識なのだろう。
話題は戻って、シダ植物について触れてみる。

シダ植物といえば、水辺や森の湿気の多いところに生えているイメージがある。
シダは太古の昔に繁栄した植物種だけれども、針葉樹や広葉樹といったタネを形成する植物らが誕生してから、生育地域を追いやられたと考えられている植物種である。
森の形成には事前にシダや低木が必要であるとすると、

こんな感じで木を植える前に、シダ植物が好むような湿気が広がっていないといけないわけで、湿気といえば草が密に茂ることから始まるだろうから、植林(植樹)の現時点での最適解は、ある程度の背丈の草のタネを蒔くことからなのでは?と考えられる。
よくある生態学の教科書では、

森の一歩手前はススキの草原になるわけで、イネ科の草がシダを育む環境を準備するのだろうな。
ハゲ山の植林(植樹)はススキのタネを蒔くことから始めることが良いのかもしれない。
関連記事




