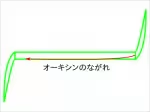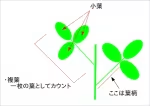/** Geminiが自動生成した概要 **/
遣唐使が持ち帰った朝顔の種は、当初薬用として利用されていました。下剤としての効能を持つ牽牛子(けんごし)がそれで、現在私たちが観賞する朝顔とは大きく異なる小さな花を咲かせます。奈良時代末期に薬用として導入された朝顔は、江戸時代に入り観賞用として品種改良が盛んに行われました。特に文化・文政期の大ブームでは、葉や花の形に様々な変化が現れた「変化朝顔」が誕生し、珍重されました。現代では見られないほど多様な変化朝顔は、浮世絵にも描かれるなど当時の文化に大きな影響を与えましたが、明治時代以降は衰退し、現在はその一部が保存されているに過ぎません。