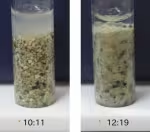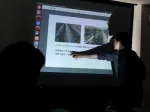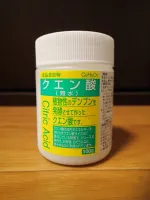/** Geminiが自動生成した概要 **/
土壌分析で高ECやリン酸過剰を示した場合、緑肥を栽培しすき込むことで改善が見込まれる。緑肥は土壌に高密度で根を張り巡らせ、リン酸などを吸収する。すき込み後は団粒構造の形成に寄与し、過剰分の悪影響を軽減する。しかし、炭酸石灰については、緑肥によって消費されるものの、植物体内でカルシウムは繊維質強化や酵素活性に利用され、最終的には土壌中に戻ってしまう。ミミズの働きで炭酸塩として再固定されるため、窒素やリン酸ほど顕著な減少は見られない。ただし、緑肥栽培による土壌物理性の向上、特に排水性向上により、過剰なカルシウムイオンが土壌深層へ移動する可能性がある。緑肥栽培は、硫酸石灰過多にも効果が期待できる。物理性の向上は、様々な土壌問題の解決に繋がる。