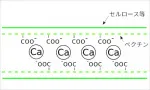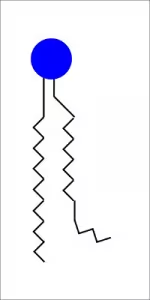/** Geminiが自動生成した概要 **/
老木は、繰り返し剪定されながらも長い年月を生き抜いてきた。樹皮は剥がれ、辺材は朽ち果てているが、それでもなおそこに立っている。剥がれ落ちた樹皮は根元に堆積し、土へと還りつつある。やがて自身も朽ちて土になることを考えると、木は自身を周りの環境と一体化させながら生涯を終えることになる。この木の姿を見て、そのような心境はどのようなものかと思いを馳せた。関連記事「木の新陳代謝と地衣類たち」の要約は提供できません。記事の内容が提供されていないためです。記事へのアクセスがあれば要約を作成できます。