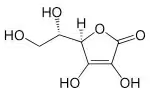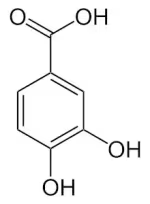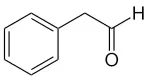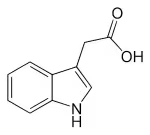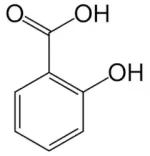/** Geminiが自動生成した概要 **/
石灰窒素(CaCN₂)の作用機序を解説。水に溶けると、強い殺菌・殺虫・除草作用を持つ「シアナミド」と、土壌pHを上げる「消石灰」に分解されます。シアナミドは土壌中で加水分解され尿素となり、さらに微生物の働きでアンモニウムイオン(植物の窒素源)と炭酸イオン(土壌pH上昇に寄与)に変化。この一連の作用により、石灰窒素は土壌のpHを上昇させ、カルシウム肥料および窒素肥料として機能することが明確になりました。シアナミドの農薬的な働きについては、次回以降で詳述します。